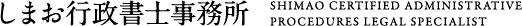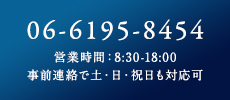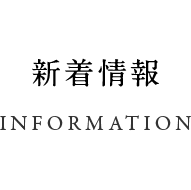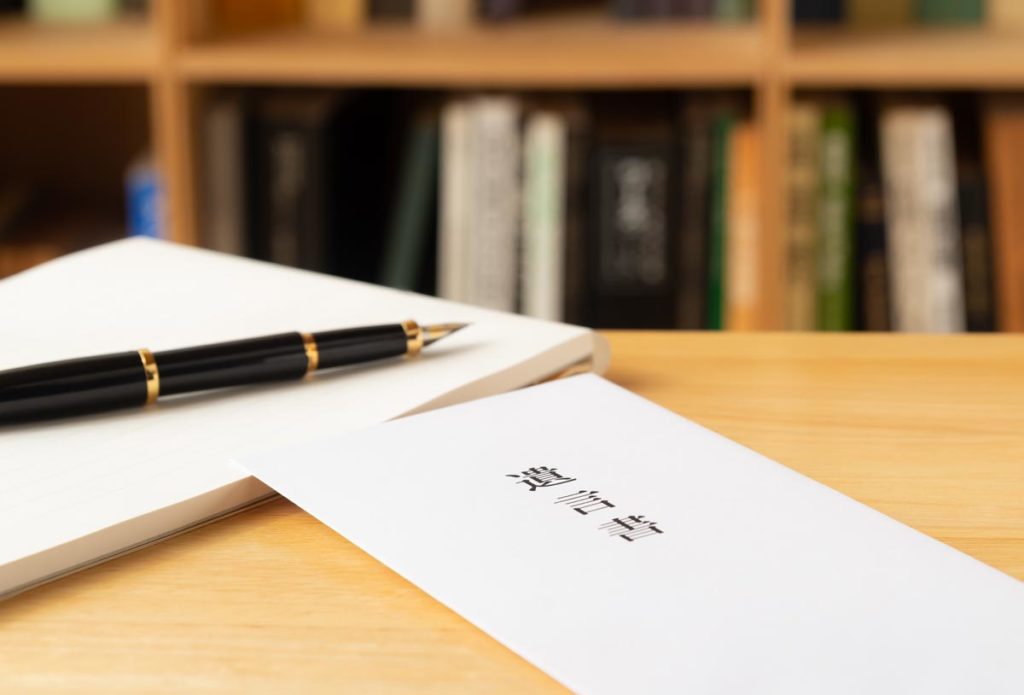ー遺言書の遺産分割でトラブルを防ぐには?基本と注意点を解説ー
2025.06.20
遺言書がある場合の遺産分割の流れとポイント
相続において重要な役割を果たすのが「遺言書」です。遺言書があることで、故人の意思を尊重した形で遺産を分けることが可能となり、相続人同士のトラブルも防ぎやすくなります。しかし、遺言書の内容がすべての相続人にとって納得のいくものとは限らず、誤解や混乱が生じるケースもあります。この記事では、「遺言書の遺産分割」に関する基本知識や注意点を初心者にもわかりやすくご紹介します。
遺言書がある場合の基本的な流れ
遺言書がある場合、原則としてその内容に従って遺産を分けることになります。ただし、形式や記載内容に不備があると無効になることもあるため、まずは遺言書の種類と効力を確認することが大切です。
・自筆証書遺言:全文を自筆で書いたもの。2020年以降は法務局での保管制度も開始。
・公正証書遺言:公証人立ち合いのもと作成される最も確実な形式。
・秘密証書遺言:内容は秘密にされるが、形式が複雑で利用は少なめ。
有効な遺言書が見つかれば、原則としてその内容に沿って遺産分割が行われます。ただし次のような点に注意が必要です。
遺留分と遺産分割の関係
遺言書で特定の相続人に全財産を相続させる旨が書かれていた場合、他の相続人がまったく財産を受け取れない可能性があります。しかし、法律では「遺留分」という制度があり、一定の法定相続人には最低限の権利が保障されています。
・遺留分の対象者:配偶者、子、直系尊属(親など)
・遺留分の割合:直系の相続人が複数いる場合は全体の1/2
遺言によって遺留分を侵害された相続人は「遺留分侵害額請求」を行うことで、相応の財産を取り戻すことができます。
遺言書の内容をめぐる相続トラブルは、この遺留分が関係することが多いため、内容確認と対応が重要です。
相続人同士の合意が必要なケース
遺言書があっても、すべての財産について詳細な分割方法が指定されていない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。以下のような場合が該当します。
・遺言書に書かれていない財産がある
・遺言の一部だけが無効と判断された
・遺言書の内容に相続人全員が納得し、話し合いで変更したい
このようなときは、法定相続人全員で協議を行い、合意内容を「遺産分割協議書」として文書にまとめます。署名押印した書類は、不動産の登記や銀行手続きにも必要です。
まとめ
遺言書があることで遺産分割の手続きは基本的にスムーズに進みますが、すべてが円満に解決するとは限りません。遺留分の確認や協議が必要なケースもあるため、相続人全員が内容を理解し、必要に応じて専門家に相談することが大切です。遺言書の正しい扱い方を知ることで、相続のトラブルを未然に防ぎ、円滑な手続きを進めることができます。
遺言・相続、外国人の在留手続き、日本語学校設立申請は大阪市東淀川区のしまお行政書士事務所にお任せ下さい。
住所:〒533-0021 大阪府大阪市東淀川区下新庄6丁目4番地3号 ジュンハイツ第二505
TEL/FAX:06-6195-8454
営業時間:月曜日-金曜日/8:30~18:00
業務内容:遺言・相続、外国人の在留手続き