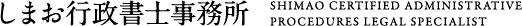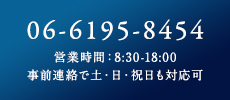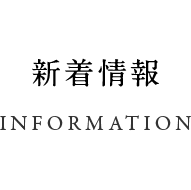ー遺言書の必要書類 完全ガイドー
2025.10.17

遺言書の種類と必要書類の全体像
遺言書は大きく自筆証書遺言と公正証書遺言に分かれます。どちらも「誰が相続人か」「どんな財産があるか」「本人の意思が明確か」を証明できる裏付け資料が鍵です。まず全体像を掴んでから、自分の方式に合う書類を段取りよく集めると迷いません。
自筆証書遺言に準備する書類
1 自分の本人確認書類
2 相続人を確認するための戸籍謄本一式
3 財産目録と裏付け資料の写し
4 署名捺印に使う印鑑
5 法務局保管制度を使うなら申請書と手数料
本文は全文自書が原則ですが、財産目録はパソコン作成でも構いません。目録と遺言本文をホチキスで綴じず、各ページに署名又は記名押印を添えると後の確認がスムーズです。
公正証書遺言に準備する書類
1 本人確認書類
2 印鑑証明書
3 相続人全員の戸籍関係書類
4 財産の資料一式
5 証人二名の氏名住所生年月日と本人確認書類
公証役場で公証人が内容を確認し作成します。事前に公証役場へ相談し、必要書類の有効期限や文言のポイントを確認してから予約すると効率的です。
財産別の裏付け資料
1 不動産は登記事項証明書と固定資産評価証明書
2 預貯金は通帳の写しや残高証明
3 有価証券は証券会社の残高報告書
4 生命保険は保険証券の写し
5 事業資産は貸借対照表や契約書の写し
財産を列挙するだけでなく、どの口座や地番を指すのか特定できる資料を添えるほど、執行段階での手戻りが減ります。
相続人と受遺者の確認書類
1 相続人の戸籍謄本
2 受遺者がいる場合は住民票
3 亡くなった配偶者や子がいる場合は除籍謄本改製原戸籍
4 遺言執行者を指定するなら氏名住所連絡先
家族関係が複雑な場合は、出生から現在まで連続する戸籍の収集が必要になることがあります。早めに市区町村窓口や郵送請求の手順を確認しておきましょう。
書類収集をスムーズに進めるコツと注意点
必要書類は発行元や有効期限がばらばらです。先に時間がかかる戸籍類と登記事項証明を請求し、次に残高証明など日付が新しい方が望ましい資料をそろえると全体の整合性が保てます。
収集手順の例
1 財産リストを作る
2 相続関係説明図を下書きする
3 役所で戸籍住民票印鑑証明を請求
4 法務局やオンラインで不動産の証明書を取得
5 金融機関で残高証明を取得
6 公証役場へ事前相談と予約
順番を決めて動けば、取り寄せ待ちの時間も有効活用できます。相続人の連絡先や証人候補もこの段階で固めておくと当日の手続きが滞りません。
よくある不足と対処
1 相続人の一部の戸籍が欠けている
2 不動産の地番と住所が一致しない
3 証人の要件を満たしていない
4 旧姓や通称での表記ゆれ
不安な点は書士や公証役場に早めに確認し、読み手が一度で理解できる表記に統一します。付言事項で家族への思いを残すと、解釈の行き違いも減らせます。
法務局の自筆証書遺言保管制度を使う場合
1 保管申請書
2 遺言書原本
3 本人確認書類
4 手数料
保管証が発行されるため、相続開始後の家庭裁判所の検認が不要になります。相続人が内容を確認する際の取得方法も生前に伝えておくと安心です。
まとめ
遺言書は「本人確認」「相続関係」「財産特定」の三本柱を裏付ける資料の整え方で成否が分かれます。今日から財産リストと戸籍収集に着手し、公証役場や専門家に下書き段階で相談すれば、無理なく確実な遺言づくりが進められます。
遺言・相続、外国人の在留手続き、日本語学校設立申請は大阪市東淀川区のしまお行政書士事務所にお任せ下さい。
住所:〒533-0021 大阪府大阪市東淀川区下新庄6丁目4番地3号 ジュンハイツ第二505
TEL/FAX:06-6195-8454
営業時間:月曜日-金曜日/8:30~18:00
業務内容:遺言・相続、外国人の在留手続き